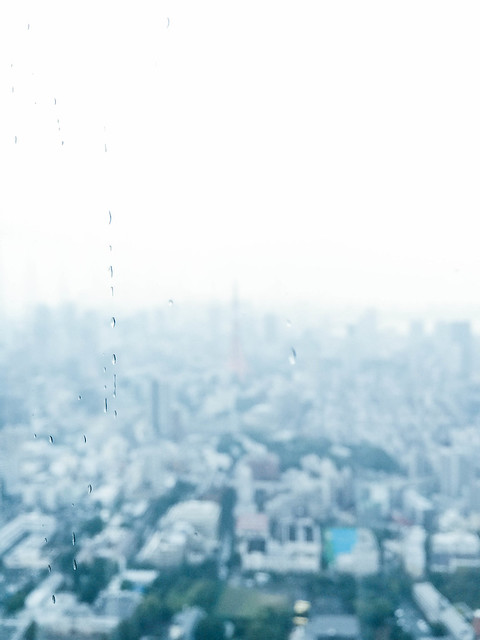ときどき、深い夢をみる。たいていの夢と同じように意味不明だけれど、やけに静かで、どこかもの寂しい夢。
ぼくは9階建てのマンションの8階に住んでいるようだった。なぜかエレベータはなく、階段を駆け足で降りていった。そこから少し歩いたのか、電車に乗って別の町に出かけたのかはわからない。砂利が敷かれてあちこちに雑草が生えている駐車場と道路を仕切るフェンスに掛けられた看板を眺めていた。ぼくは何かをあきらめて、近くにあった小さな一階建ての建物のドアを開けた。中に入るとそこはいくつかの商店が集まった屋内商店街のようだった。入ってすぐ右手の店のおばさんがぼくを見ている。それを無視して真ん中の通路をどんどん歩いていく。ほとんどの店に人は立っていない。営業時間外なのか、店を畳んだのかはわからない。小さい建物なのですぐに一番奥まで辿り着いた。奥のドアを開け立ちすくんでいると、最後の店のおじさんが声をかけてくる。ぼくは「おいしいアンパンがあると聞いて買いに来たのだが、見つからなかった」と説明する。おじさんはぼくを建物に戻るよう促し、入ってすぐの自分の店へと戻っていった。おじさんの店の壁に備え付けられた棚にいくつかの籠があって、そこには2,3個ずつパンが盛られていた。それらの籠のうちのひとつにアンパンがあった。アンパンはカレーパンのように揚げられているようだった。ぼくは2つくださいと頼み、おじさんは透明のナイロン袋にアンパンを2つ入れてくれた。以前、台湾旅行中に屋台で見た記憶のある特殊な方法でナイロン袋の口を縛ってくれた。ぼくはおじさんの様子を観察しながら、大きなテーブルの前に置かれたイスに座って待っていた。ふと気が付くと隣には女の子が座っていた。高校生くらいに見えたが、手には火のついてタバコを持っていた。左手にタバコを持ち、テーブルに伸ばした左腕を枕にして頭を乗せてぼーっとしていた。後ろのドアが開いている。ここは海の近くの高台にあるようで、眼下に海が見えた。とても静かでうつくしい景色だった。ドアの向こうから女の子の帰宅を促す母親の遠い声が聞こえたが、女の子はそれを無視しているようだった。おじさんは、サービスのつもりか、アンパンの中身となる餡が余っていたので大福を作ってくれていた。餅に餡を包む手つきは和菓子職人のそれだった。そうこうしていると、なぜか今度は白い平皿に盛られた玉子と野菜の中華炒めが出てきた。注文した覚えはないが、そこに違和感を覚えることなく、美味しそうだと思った。あまりに美味しそうだったので、添えられた細長い銀色のスプーンで一口分をすくい、隣で突っ伏している女の子に食べさせてやった。